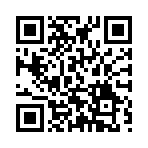2009年06月19日
ビーダマコースター@アートスクール
今月のアートスクールは「リサイクル工作」
うちにある廃材を材料にして『新しい何かをつくりだす』工作体験です。
今年の素材は「牛乳パック」
牛乳パックは すぐれものですね!。
加工しやすい。紙が丈夫。サイズが一定。手に入りやすい(どこの家にもある)。
6/13(土)
この牛乳パックを使って、作って遊べる『ビーダマコースター』を作りました
初めに作り方を聞きます。みんな、真剣な表情~

製作始まりました。会場はこんな感じ。
レールを作って、2本のタワーにコースを作っていきます。


牛乳パックを『切って』 『形を作って』 『貼り付けていく』
さすが、高学年の子どもたちは、それぞれに工夫して作っていきます!
低学年の子どもたちは、自分が思うように作るのは、ちょっと難しいかな。。!?
10時~12時、休憩をとることもなく、みんな集中して作りましたが、
予定の2時間はあっという間にすぎ、完成がもうすぐ!というところで時間がきてしまいました。
続きは家で・・ということになりましたが、
製作途中では、ビーダマを何度も転がしてみて、ビーダマがコースを上手く走っていく醍醐味を味わった人もいましたね!
午後からは、希望者の方々が場所をきっずコム事務所に移して、続きの製作。
完成をめざして、がんばりました。

タワーを2階建てに工夫

ここをもっと高くしてスピードが出るようにしよう!
~遊びながら、どんどんイメージがひろがっていきます。

がんばるぞ
完成! 自慢の作品を手に、記念にパチリ
自慢の作品を手に、記念にパチリ
*************
今回のリサイクル工作は、
「目的が違う全然別の捨ててしまうもの」を使って「遊べるおもちゃを作る」という
無から有を自分の手で生み出す作業でした。
過程では、道具を使いました。
ものさしで長さを計りました。
硬い紙に『まっすぐ』直線を引きました。
はさみやカッターという刃物も使いました。
ビーダマが転がるには、どんな力や工夫がいるのだろうか?
スムーズにゴールするにはどうしたらいいんだろうか?
何度も失敗して、作り変えて、細かく調節することも、あきらめずに繰り返しました。
子どもたちにとっては、高いハードルだったかも知れません。でも、すべて『体験』なのだと思います。
子どもたちの日常に、こんなふうにして自分の手で工作して作って遊ぶという事が少なくなっているのでは・・・・?!と、ちょっと思いました。
学校の現場では、どうなのでしょうか?!このような工作の機会はあるのでしょうか。
でも、今回のここでの作業って、ひっくるめて言うと【生活力】なんだよね~
このような
手や道具を使うこと、
失敗してもまたチャレンジしていく、
そんな体験の積み重ねが、子どもたちの【生きる底力】となってくれたらなあ・・と思ったのでした。
うちにある廃材を材料にして『新しい何かをつくりだす』工作体験です。
今年の素材は「牛乳パック」
牛乳パックは すぐれものですね!。

加工しやすい。紙が丈夫。サイズが一定。手に入りやすい(どこの家にもある)。
6/13(土)
この牛乳パックを使って、作って遊べる『ビーダマコースター』を作りました
初めに作り方を聞きます。みんな、真剣な表情~


製作始まりました。会場はこんな感じ。

レールを作って、2本のタワーにコースを作っていきます。


牛乳パックを『切って』 『形を作って』 『貼り付けていく』
さすが、高学年の子どもたちは、それぞれに工夫して作っていきます!
低学年の子どもたちは、自分が思うように作るのは、ちょっと難しいかな。。!?
10時~12時、休憩をとることもなく、みんな集中して作りましたが、
予定の2時間はあっという間にすぎ、完成がもうすぐ!というところで時間がきてしまいました。

続きは家で・・ということになりましたが、
製作途中では、ビーダマを何度も転がしてみて、ビーダマがコースを上手く走っていく醍醐味を味わった人もいましたね!
午後からは、希望者の方々が場所をきっずコム事務所に移して、続きの製作。
完成をめざして、がんばりました。

タワーを2階建てに工夫

ここをもっと高くしてスピードが出るようにしよう!
~遊びながら、どんどんイメージがひろがっていきます。


がんばるぞ

完成!
 自慢の作品を手に、記念にパチリ
自慢の作品を手に、記念にパチリ
*************
今回のリサイクル工作は、
「目的が違う全然別の捨ててしまうもの」を使って「遊べるおもちゃを作る」という
無から有を自分の手で生み出す作業でした。
過程では、道具を使いました。
ものさしで長さを計りました。
硬い紙に『まっすぐ』直線を引きました。
はさみやカッターという刃物も使いました。
ビーダマが転がるには、どんな力や工夫がいるのだろうか?
スムーズにゴールするにはどうしたらいいんだろうか?
何度も失敗して、作り変えて、細かく調節することも、あきらめずに繰り返しました。
子どもたちにとっては、高いハードルだったかも知れません。でも、すべて『体験』なのだと思います。
子どもたちの日常に、こんなふうにして自分の手で工作して作って遊ぶという事が少なくなっているのでは・・・・?!と、ちょっと思いました。
学校の現場では、どうなのでしょうか?!このような工作の機会はあるのでしょうか。
でも、今回のここでの作業って、ひっくるめて言うと【生活力】なんだよね~
このような
手や道具を使うこと、
失敗してもまたチャレンジしていく、
そんな体験の積み重ねが、子どもたちの【生きる底力】となってくれたらなあ・・と思ったのでした。

Posted by きっずコム at 21:24│Comments(0)
│きっずコム